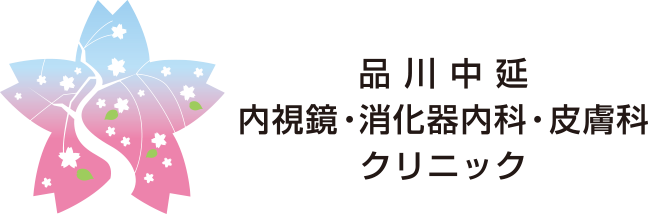潰瘍性大腸炎について

潰瘍性大腸炎は炎症性腸疾患の一つで大腸粘膜に慢性的な炎症が起こり、潰瘍やびらんが形成される病気です。炎症が起こる活動期(再燃期)と炎症が治まる寛解期を繰り返します。自己免疫によって発症するといわれていますが、その発生機序についてははっきりとしていません。免疫異常によってTNF-αが過剰に作られることで、炎症が発生することは分かっています。このように原因がはっきりとしないことから完治させる治療法が確立されておらず、厚生労働省から難病に指定されています。なお、医師の指示にしたがって治療を続けることで、症状が落ち着く寛解期に移行し、以前とほぼ変わらない生活を送ることが可能です。しかし、放置すると、炎症が重症化して様々な合併症を招き、入院を伴う手術が必要になります。
なお、手術や入院が必要な場合は連携先の医療機関をご紹介します。
クローン病と似た症状を示しますが、炎症範囲や治療法などは違いがあるため、鑑別診断が欠かせません。
潰瘍性大腸炎の症状
発症初期は腹痛や下痢、血便などが主な症状となります。炎症が起こる活動期(再燃期)と炎症が治まる寛解期を繰り返す特徴があり、悪化すると貧血や発熱、体重減少などが起こります。まずは寛解期を目指して治療し、治療を継続して寛解期を保つことが大切です。寛解期も症状が治まったからといって自己判断で治療を中断すると、再燃期に移行する恐れがあります。また、大腸の炎症が慢性化すると大腸がんの発症リスクが上がるため、定期的に大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。
潰瘍性大腸炎の合併症
粘膜下層にまで炎症が到達すると、腸管の狭窄や穿孔、大量出血、腸内にガスが溜まり中毒症状が起こる巨大結腸症など深刻な合併症を招く恐れがあります。また、腸管の他にも、目や皮膚、口腔内、胆道系、関節に合併症が生じることもあります。
潰瘍性大腸炎の検査・診断
まずは問診にて症状の内容や経過などについてお聞きします。血便が出た場合、パニックになってしまうかもしれませんが、落ち着いて血液の量や色、粘液の有無などを確認し、医師に詳細をお伝えいただければ診断がスムーズになります。
潰瘍性大腸炎で起こる症状は他の炎症性腸疾患でも起こり得るため、大腸カメラ検査やレントゲン検査、CT検査などにより詳しく確認していきます。大腸カメラ検査は大腸粘膜を直接観察でき、びらんや潰瘍など潰瘍性大腸炎特有の病変を発見することが可能です。疑わしい病変が見つかった場合、一部組織を採取して病理検査に回すことで確定診断の助けになります。CT検査が必要な場合、当院の連携先である高度医療機関をご紹介します。
潰瘍性大腸炎の治療
炎症が起きている活動期(再燃期)では、炎症をできるだけ早く鎮め、寛解期へ導くことが目標になります。治療は薬物療法が中心となり、5-ASA製剤によって炎症を鎮めます。なお、強い炎症が起きている場合はステロイド剤を短期的に使用します。5-ASAは寛解期を維持するためにも有用なため、寛解期に移行後も継続して使用します。その他、免疫調整薬や生物学的製剤(抗TNF-α抗体)、抗菌薬を使用することもあります。
日常生活でのご注意
炎症が落ち着く寛解期では発症前とほぼ変わらない生活を送れます。厳しい制限事項はないですが、炎症の悪化・再燃を防ぐためにも腸に負担がかかるような行動は控え、健康的な生活を送ることが大切です。
食事
腸への負担が大きい暴飲暴食や香辛料などの刺激物の過剰摂取はお控えください。それ以外は特に制限事項はありません。
運動
激しい運動は控え、軽い有酸素運動を習慣的に行いましょう。やや速足での散歩や水泳などがお勧めです。
アルコール
寛解期ではアルコールの過剰摂取は控え、適量に留めましょう。
潰瘍性大腸炎のある方の
妊娠と出産
 寛解期を維持した状態であれば、妊娠・出産・授乳を行えます。再燃期に移行しないように医師の指示にしたがって治療を続けましょう。妊娠が判明したことで慌てて治療を中断してしまうと母体や胎児に影響が出る恐れがあるため、妊娠が判明した場合は速やかに当院までご相談ください。妊娠を希望されている場合、予め妊娠時の対処法や治療方針について相談しておくと安心です。
寛解期を維持した状態であれば、妊娠・出産・授乳を行えます。再燃期に移行しないように医師の指示にしたがって治療を続けましょう。妊娠が判明したことで慌てて治療を中断してしまうと母体や胎児に影響が出る恐れがあるため、妊娠が判明した場合は速やかに当院までご相談ください。妊娠を希望されている場合、予め妊娠時の対処法や治療方針について相談しておくと安心です。
クローン病について
クローン病は、小腸・大腸を中心に口から肛門に至る消化管全域で慢性的な炎症が発生し、潰瘍やびらんが形成される病気です。潰瘍性大腸炎と同様に、症状が起こる活動期(再燃期)と症状が落ち着く寛解期を繰り返す特徴があります。
自己免疫によって発症するといわれていますが、その発生機序についてははっきりとしていません。潰瘍性大腸炎と同じく、免疫異常によってTNF-αが過剰に作られることで、炎症が発生することは分かっています。完治させる治療法がないことから、厚生労働省より難病に指定されています。
このようにいくつか共通点がありますが、炎症範囲や治療法などに違いがあるため、鑑別診断が欠かせません。炎症が発生する場所に応じて小腸型、小腸・大腸型、大腸型の3つのタイプに分けられ、それぞれ適切な治療法が異なります。適切な治療を続けて病状をコントロールすることで、発症前とほぼ変わらない生活を送れます。なお、治療を中断すると再燃期に移行する可能性があるため、寛解期に移行後も治療を続けることが大切です。また、クローン病は潰瘍性大腸炎よりも炎症が深部にまで及びやすく、重大な合併症を招く恐れがあるので注意しましょう。気になる症状があれば、一度当院までご相談ください。
クローン病の症状
発症初期は腹痛や下痢などが起こりますが、炎症が悪化すると、発熱や体重減少、血便、粘血便などの症状が起こります。他にも、消化管全体に炎症が拡がることで口内炎、切れ痔、肛門周囲膿瘍、痔ろうなどが起こることもあります。活動期(再燃期)と寛解期を繰り返す特徴があります。そのため、症状が治まったと自己判断で治療を中断せず、寛解期も医師の指示にしたがって治療を続けましょう。
クローン病の合併症
クローン病の炎症は粘膜の浅い層から発生しますが、少しずつ粘膜下層にまで広がっていき、深部にまで到達すると、腸管の狭窄や穿孔、膿瘍、消化管から皮膚や他臓器を繋ぐ瘻孔などの深刻な合併症を招きます。また、滅多にありませんが、大量出血、大腸がん、肛門がんなどが起こることもあります。それ以外にも、目や皮膚、口腔内、胆道系、関節に合併症が生じることもあります。
クローン病の検査・診断
まずは問診にて症状の内容や経過などをお聞きします。血便が出た場合、パニックになってしまうかもしれませんが、落ち着いて血液の量や色、粘液の有無などを確認し、医師に詳細をお伝えいただければ診断がスムーズになります。クローン病で起こる症状は他の炎症性腸疾患でも起こり得るため、大腸カメラ検査やレントゲン検査、CT検査などにより詳しく確認していきます。大腸カメラ検査は、びらんや潰瘍などクローン病特有の病変を発見することが可能です。疑わしい病変が見つかった場合、一部組織を採取して病理検査に回すことで確定診断を下せます。
クローン病の治療
クローン病は主に薬物療法を行います。炎症を抑えて寛解期へ導き、その状態を維持することが目標となります。また、クローン病は特定の食品により腸管が刺激されて症状が悪化することがあるため食事制限を行い、不足した栄養分を栄養療法により補うこともあります。こうした保存療法では効果が不十分な場合、深刻な合併症が起きた場合に手術を行うこともあります。なお、手術が必要な場合は連携先の医療機関をご紹介します。
栄養療法
クローン病では特定の食品により腸管が刺激されて症状が悪化することがあり、炎症が拡大すると栄養不良に陥る可能性があります。この場合、消化管を休ませつつ栄養状態を改善するために栄養療法を行います。栄養療法は、口や鼻から栄養剤を投与する経腸栄養療法と点滴から栄養輸液を投与する完全静脈栄養療法があります。経腸栄養療法は消化が必要になる半消化態栄養剤、消化が必要ない消化態栄養剤や成分栄養剤に分けられます。完全栄養療法は、小腸病変が広範囲に及ぶ場合や重度の狭窄が起きている場合に実施します。
食事制限
刺激となる食品は人によって違うため、その食品を把握することが必要です。なお、怪しいという理由から過度に食事を制限してしまうと栄養不良に陥り、かえって免疫力の低下や他の病気に繋がる可能性があるため、医師の管理のもと食事制限を行いましょう。
薬物療法
活動期(再燃期)と寛解期は、いずれも5-ASA製剤を使用します。また、活動期ではステロイドも併用し、なるべく早めに寛解期へ導けるよう努めます。その他、免疫調整薬や生物学的製剤(抗TNF-α抗体)、抗菌薬を使用することもあります。
日常生活でのご注意
寛解期を維持することで発症前とほぼ変わらない生活を送れます。なお、寛解期で治療を中断すると再燃期へと移行する可能性があるため、寛解期も医師に指示にしたがって治療と食事制限を続けることが必要です。
食事
炎症が落ち着く寛解期では厳しい制限はありません。しかし、基本的には消化管への負担が少ない低脂肪で食物線維があまり含まれていない食事が望ましいです。
また、症状の悪化を招く食品は控えてください。なお、病変の状態や範囲によって症状を悪化させる食品は異なるため、日々の食事の記録を付けて食べて良いものと控えるべきものを把握するようにしましょう。
運動
身体に負担がかかる激しい運動は控え、無理のない範囲で取り組めるストレッチや散歩など軽い有酸素運動を習慣化しましょう。
アルコール
寛解期ではアルコールの過剰摂取は控え、適量を心がけましょう。
喫煙
タバコを吸うことでクローン病の悪化・再燃を招く恐れがあるため、禁煙が必要となります。
クローン病のある方の
妊娠と出産
 潰瘍性大腸炎と同様に、クローン病でも寛解期を維持した状態であれば妊娠・出産・授乳を行えます。再燃期へ移行しないよう医師の指示にしたがって治療を続けましょう。妊娠が判明したことで慌てて治療を中断してしまうと母体や胎児に影響が出る恐れがあるため、妊娠が判明した場合は速やかに当院までご相談ください。妊娠を希望されている場合、予め妊娠時の対処法や治療方針について相談しておくと安心です。
潰瘍性大腸炎と同様に、クローン病でも寛解期を維持した状態であれば妊娠・出産・授乳を行えます。再燃期へ移行しないよう医師の指示にしたがって治療を続けましょう。妊娠が判明したことで慌てて治療を中断してしまうと母体や胎児に影響が出る恐れがあるため、妊娠が判明した場合は速やかに当院までご相談ください。妊娠を希望されている場合、予め妊娠時の対処法や治療方針について相談しておくと安心です。