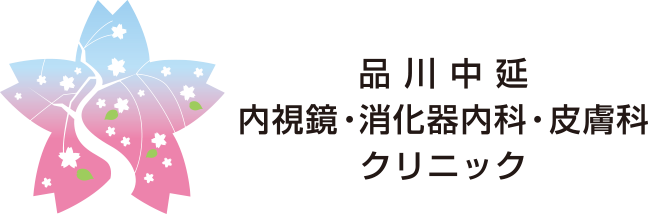食道の病気
食道がん
食道がんは、喫煙や飲酒などが原因となります。また、逆流性食道炎やバレット食道の患者様は発症リスクが高まります。初期は自覚症状が乏しいですが、食道粘膜は他の臓器と違って外側に漿膜がないため転移リスクが高く、重症化した場合は手術の難易度が上がります。なお、初期段階で発見できれば内視鏡的治療により完治が見込めます。そのため、胃カメラ検査を定期的に受けて早期発見・早期治療に努めましょう。
逆流性食道炎(GERDガード:gastroesophageal reflux disease)

逆流性食道炎とは、胃酸を含む胃液が食道に逆流し、食道粘膜に炎症を引き起こす病気です。胸焼けなど様々な症状を示します。一方、胃カメラ検査などを行っても炎症が見つからないにもかかわらず、胸焼けなどの症状が続く病気を非びらん性胃食道逆流症(NERDナード:non-erosive reflux disease)と呼びます。炎症が起こっていないものの、胃酸の逆流や食道の知覚過敏などが原因となって症状が起きるといわれています。
治療は生活習慣の改善と薬物療法を行います。薬物療法では、胃酸分泌抑制薬や胃酸中和薬などを使用します。
好酸球食道炎
好酸球食道炎とは、好酸球という白血球が食道粘膜に集まり、慢性的な炎症を引き起こす病気です。特定の食物などに対するアレルギー反応が原因となることがありますが、アレルゲンがはっきりとしないこともよくあり、厚生労働省から難病として指定されています。若年層に好発しますが、成人に認められることも稀にあります。胸のつかえ感や胸焼けなど逆流性食道炎と似た症状を示すため、胃カメラ検査による鑑別診断を行う必要があります。なお、現在のところ完治させる方法がないため、治療は薬物療法による対症療法となります。炎症を抑える胃酸分泌抑制剤、アレルギー反応を抑える抗アレルギー薬やステロイド薬を使用します。
食道裂孔ヘルニア
食道裂孔ヘルニアは、食道にある横隔膜から胃の上部が胸部に飛び出す病気です。姿勢の乱れや肥満、衣服などにより腹圧が上昇することで発生します。胃酸の逆流リスクが高まり、逆流性食道炎が発生する可能性があります。胃カメラ検査によりヘルニアの程度や炎症の有無を調べ、炎症があれば逆流性食道炎と同様の治療を行います。軽症の場合、生活習慣を改善して腹圧を低下させ、胸焼けなどの症状には胃酸分泌抑制剤などを用いた薬物療法を実施します。
バレット食道
バレット食道は、食道粘膜を覆う扁平上皮が何らかの原因で胃粘膜である円柱上皮に変性した状態です。原因ははっきりとしていませんが、逆流性食道炎により食道下部の粘膜が損傷し、回復する過程で扁平上皮が円柱上皮に置き換わるのではないかといわれています。主な症状には、胸焼けや胸痛などが挙げられます。診断には胃カメラ検査が有効です。バレット食道が認められる場合は、炎症を抑えるために胃酸分泌抑制薬を用いた薬物療法を行います。また、変性した細胞にはがん化リスクがある細胞が含まれ、食道がんの発症リスクがあるため、経過観察も欠かせません。
食道カンジダ症
真菌の仲間であるカンジダが食道粘膜に感染することで炎症を引き起こす病気です。カンジダは常在菌ですが、免疫力の低下や抗生剤の服用などが原因となって増殖し、炎症を引き起こします。
胸のつかえ感や胸焼け、嚥下障害など逆流性食道炎と同様の症状を示します。多くの場合、自然治癒するため経過観察での対応が基本となりますが、強い症状により生活の質(QOL)が低下している場合は抗真菌薬を用いた薬物療法を実施します。
食道異物
魚の骨や欠損した歯などは成人でも誤って飲み込んでしまうことがあります。小さな子どもの場合、プラスチックの蓋やボタン電池などを口に入れて遊んでいる間に飲み込んでしまうことがあります。こうした異物が食道で引っ掛かると、鋭利な物では食道壁を傷つけてしまう恐れがあります。特に化学物質を含むボタン電池などは、薬液が漏れ出て潰瘍や穿孔を引き起こす可能性があります。なお、こうした食道に引っかかった異物は内視鏡により除去することが可能なケースがほとんどです。異物が詰まった感覚があれば、早めに当院までご相談ください。
胃・十二指腸の病気
胃がん
胃がんの原因には、ピロリ菌感染や塩分の過剰摂取、飲酒、喫煙などが挙げられます。初期では自覚症状が乏しく、病状が悪化してから症状が起こるため、早期発見のために定期的な胃カメラ検査の受診が欠かせません。初期段階で発見することで、内視鏡による治療で完治が望めます。
ピロリ菌感染症
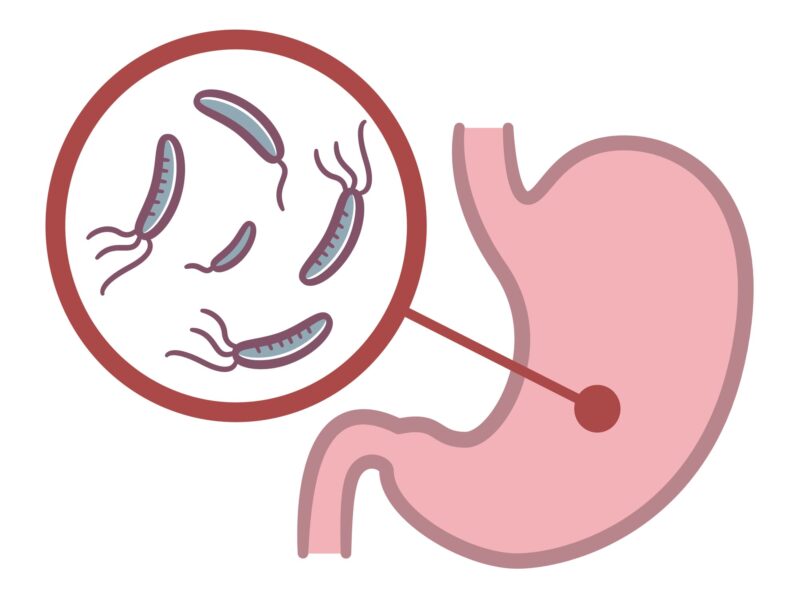 ピロリ菌は、通常微生物がすみつけないほど強い酸性の胃の内部にすみつける細菌で、正式名称は「ヘリコバクター・ピロリ菌」と呼ばれます。ウレアーゼという酵素を分泌して胃酸を中和することで胃粘膜にすみつきます。感染経路は経口感染といわれており、幼少期に井戸水や両親からの口移しにより感染することが多いです。ピロリ菌が感染すると慢性的な炎症が発生し、胃・十二指腸潰瘍に繋がる可能性があるため、除菌治療が欠かせません。
ピロリ菌は、通常微生物がすみつけないほど強い酸性の胃の内部にすみつける細菌で、正式名称は「ヘリコバクター・ピロリ菌」と呼ばれます。ウレアーゼという酵素を分泌して胃酸を中和することで胃粘膜にすみつきます。感染経路は経口感染といわれており、幼少期に井戸水や両親からの口移しにより感染することが多いです。ピロリ菌が感染すると慢性的な炎症が発生し、胃・十二指腸潰瘍に繋がる可能性があるため、除菌治療が欠かせません。
ピロリ菌は、通常微生物がすみつけないほど強い酸性の胃の内部にすみつける細菌で、正式名称は「ヘリコバクター・ピロリ菌」と呼ばれます。ウレアーゼという酵素を分泌して胃酸を中和することで胃粘膜にすみつきます。感染経路は経口感染といわれており、幼少期に井戸水や両親からの口移しにより感染することが多いです。ピロリ菌が感染すると慢性的な炎症が発生し、胃・十二指腸潰瘍に繋がる可能性があるため、除菌治療が欠かせません。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍

粘膜層に炎症が発生し、傷が粘膜層にのみできている場合は「びらん」となり、粘膜下層にまで及ぶと「潰瘍」となります。胃・十二指腸潰瘍は慢性的な炎症により潰瘍が形成された状態です。主な原因にはピロリ菌感染、ストレス、アルコール、薬の副作用などが挙げられます。発症すると胸焼けや呑酸(酸っぱいげっぷ)、胃痛、心窩部痛などの症状を示し、悪化すると潰瘍部から出血が起こり、吐血や下血などの症状が起こります。
軽症であれば胃酸分泌抑制薬や胃粘膜保護薬を使用し、出血が認められる場合は内視鏡により止血処置を実施します。ピロリ菌感染が認められた場合は除菌治療を行うことで再発リスクを大幅に低下させられます。
急性胃炎
急性胃炎とは、胃粘膜に急性の炎症が起こった状態です。主な原因にはストレスや暴飲暴食、アレルギー、薬の副作用などが挙げられます。炎症により、胃の不快感や胃痛、嘔吐などの症状を示します。安静状態を保つことにより数日で症状は治まることが多いですが、症状を強く示す場合は内服薬を用いた薬物療法を実施します。
慢性胃炎
慢性胃炎は、胃粘膜に慢性的な炎症が起こっている状態です。胃の内部は粘膜によって覆われていますが、慢性的な炎症により徐々に胃粘膜が萎縮していきます。慢性胃炎では、胃の不快感や胃痛、胸焼けなどの症状を示します。原因は薬の副作用など様々ありますが、ピロリ菌感染が8割を占めています。ピロリ菌感染によって起きている場合は除菌治療が必要です。また、症状を改善するために胃酸分泌抑制剤や胃粘膜保護薬、消化管運動機能改善薬などを使用します。
萎縮性胃炎
萎縮性胃炎とは、慢性的な炎症により胃酸を分泌する固有腺が減少・消失し、胃粘膜が萎縮した状態です。ピロリ菌感染が原因となることが多いため、除菌治療が必要です。
萎縮性胃炎は胃がんに繋がる恐れがあるため、胃カメラ検査を定期的に受けることをお勧めします。
胃びらん(びらん性胃炎)
胃粘膜の浅い層で炎症が発生し、粘膜がただれた状態です。急性であることが多いですが、炎症が慢性化することもあります。急性の炎症では、胃の不快感や胃痛、吐き気などの症状を示し、慢性では自覚症状が乏しい傾向があります。進行に伴って出血をきたすこともあります。治療は、炎症が軽度の場合は胃酸分泌抑制剤などを用いた薬物療法が中心となり、大量出血をきたしている場合は内視鏡による止血処置を行います。
胃底腺ポリープ
胃底腺ポリープとは、胃粘膜の胃底腺が大きく成長してできたポリープです。ピロリ菌に感染していない胃粘膜に発症することが多く、胃カメラ検査を行うと他の組織と同じ色となっていることが確認されます。腫瘍とは構造に違いがあり、がん化リスクは非常に低いです。ポリープが巨大化したり数が増えたりすることがありますが、治療は不要です。胃カメラ検査を定期的に行い、経過を観察します。
過形成性ポリープ
過形成性ポリープとは、胃粘膜の細胞が異常に増殖してできるポリープです。胃カメラ検査を行うとポリープ箇所は赤色となっており、通常組織と比較しはっきりとした違いが確認できます。通常は良性で、がん化リスクは非常に低く、経過観察での対応となります。なお、巨大化して2cm以上となり増加傾向があるもの、出血しやすいものについては内視鏡による切除を行うことがあります。
機能性ディスペプシア(FD:Functional Dyspepsia)
 機能性ディスペプシアとは、胃カメラ検査などを行っても器質的異常が発見されないにもかかわらず、胃痛や胃もたれなどが続く病気です。
機能性ディスペプシアとは、胃カメラ検査などを行っても器質的異常が発見されないにもかかわらず、胃痛や胃もたれなどが続く病気です。
体内に入った食物は一時的に胃に溜まり、一定量溜まると十二指腸に排出されます。しかし、この運動機能が何らかの原因で低下したり、消化管に知覚過敏が起こったりすることで、胃の不快症状が起こるのではないかと考えられています。
治療は薬物療法が中心となり、胃酸分泌抑制薬や消化管運動機能改善薬などを使用します。また、精神的ストレスが原因となることもあるため、必要に応じて抗うつ薬なども使用します。
アニサキス
アニサキスは、サケやサンマ、サバ、イカなどの海洋生物にすみつく寄生虫です。酢漬け処理や加熱が十分でない状態で魚介類を口にすると、アニサキスが胃壁などの粘膜に寄生する可能性があります。アニサキスが寄生した場合、痛みや吐き気・嘔吐などの症状を示します。
アニサキスは人間の体内にはすみつけないため、1週間ほどで死滅して症状が治まりますが、体調不良などにより胃機能が低下していると、胃壁の深層にまで侵入して胃穿孔を引き起こす恐れがあります。
アニサキス症が疑われる場合は胃カメラ検査を行い、発見した場合はスコープ先端の鉗子で除去します。魚介類を生食した後に激しい胃痛症状が起こった場合、すぐに当院までご相談ください。