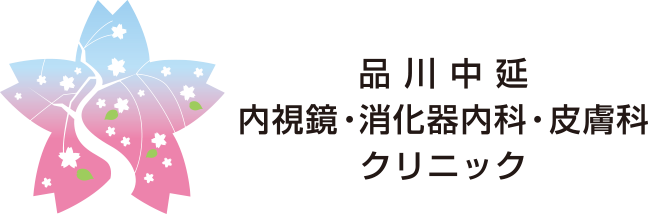帯状疱疹について

帯状疱疹について詳しく知っている方でないと不安に思うこともあるでしょう。
帯状疱疹は日頃からよく起こる病気で、日本では新規発症数が年間約50万人となっており、生涯では2,000万人以上の方が発症すると考えられています。つまり、一生涯で5~7人に1人は発症します。命を落とすほど重篤な病気ではないものの、痛みが起こるため精神的苦痛を感じる方が多いです。
治療は外用薬や内服薬を用いた薬物療法が中心となり、医師の指示にしたがって使用を続けていただきます。また、少しでも早く改善できるように、病気の内容や治療・生活における注意点などについて把握していただき、しっかり守ってもらうことも大切です。
帯状疱疹の症状
帯状疱疹では、身体の左右いずれかの神経に沿う形で、赤い斑点や小さな水ぶくれが帯状に発生し、ピリピリとした神経痛を伴います。こうした症状は1~2週間がピークとなり、4~8週ほどで落ち着きます。なお、風邪と同様に、体力や免疫力が低下している状態、安静や栄養摂取など、しっかりと体を休めて回復に努めなければ、症状が長期間続くことがあります。
皮膚症状の改善に伴って痛みも軽減していきます。激しい痛みが起きている場合、主治医に相談しましょう。
帯状疱疹と合併症
症状は全身に及ぶことがあり、目の周囲に発生した場合は視力障害が起こり、顔面に発生した場合は顔面神経麻痺を発症します。そのため、必要に応じて眼科や耳鼻科など別の診療科をご紹介することもあります。
帯状疱疹のしくみ
帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウイルスの感染が原因となります。初感染時は水ぼうそうを発症します。症状の改善後も神経節にウイルスは潜伏し続けますが、抗体によってウイルスの働きが抑えられます。なお、加齢や疲労、体力の低下、病気の発症などによりウイルスが再活性化し、皮膚や神経を刺激することで帯状疱疹が発生します。
帯状疱疹の治療
処方薬は医師から指示があった用法・容量にしたがって使用しましょう。症状が治まったからと自己判断で使用を中断した場合、悪化・再発する可能性があるため医師の指示をお守りください。
抗ウイルス薬
(バルトレックスなど)
原因となる水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を防ぐ効果があります。内服薬を基本的に使用しますが、入院を伴う重症例では点滴により体内に投与することもあります。また、症状が非常に軽度の場合、外用薬を使用することもあります。
効果は使用から2~3日ほど経過してから現れます。効果がすぐに現れないからといって中断するのは控えましょう。
外用薬(塗り薬)
外用薬は皮膚の保護、再生促進、二次感染を防止するために使用します。
鎮痛薬
帯状疱疹は痛みも伴います。そのため、非ステロイド系の消炎鎮痛薬も使用します。
神経ブロック要確認
患部の神経周囲に注射で局所麻酔薬を投与する治療です。激しい痛みが起きている場合に行いますが、高度な技術が必要となるため麻酔科やペインクリニックのある医療機関をご紹介します。
帯状疱疹の予防接種について
帯状疱疹の予防接種は生ワクチンと不活化ワクチンがあり、当院でも対応しています。以前は幼児の定期接種として用いられていた水痘ワクチンですが、2016年3月より50歳以上の方を対象に帯状疱疹の予防接種として承認されました。
今年度より、65歳以上は定期摂取となります。ワクチンをご希望の方は当院までご相談ください。
帯状疱疹のよくある質問
帯状疱疹を発症しても普段通り生活して大丈夫ですか?
帯状疱疹は心身の疲労をきっかけに発症します。風邪と同様に、早く改善するためにもしっかり栄養を摂り、十分に休みましょう。気になる症状があれば、当院までご相談ください。
休養期間はどれくらいですか?
皮膚に発生した水ぶくれがかさぶたとなった場合、普段通りの生活に戻していただいて大丈夫です。なお、休養期間中は身体を動かす機会が少ないため、筋力が低下しています。そのため、いきなり戻すのではなく、徐々に戻していきましょう。
帯状疱疹を発症しても仕事を続けて大丈夫ですか?
仕事の内容によるので一概にはいえませんが、改善するには休養が最も大切です。風邪と同様に、無理をしないように注意が必要です。
入浴は問題ありませんか?
湯船に浸かることで痛みが軽減する可能性があります。石鹸も使っていただいて大丈夫です。お風呂から上がった後は清潔なタオルで軽くなでるように水気を拭き取りましょう。外用薬を処方されている場合、入浴後に使用してください。
患部を消毒しますか?
消毒は行いません。清潔な状態を保つためにシャワーでしっかり洗い流しましょう。また、外用薬を処方されてガーゼを貼っている場合、剥がす時に痛みを感じることがあるので、シャワーで濡らしてから剥がすことをお勧めします。
飲酒しても大丈夫ですか?
アルコールは血管を拡げる作用があり、炎症が悪化する可能性があります。
帯状疱疹により皮膚・神経に炎症が発生している間は禁酒としましょう。
痛みは冷すべきでしょうか?あるいは温めるべきでしょうか?
人によって異なりますが、冷やすことで痛みが強くなります。適度な温度で患部を温めることで痛みが緩和することが多いです。なお、使い捨てカイロなどを患部に直接貼ると火傷になる恐れがあるため控えましょう。
我慢できないほど痛みが強い、もしくは皮膚症状が解消しても痛みが残る場合、当院までご相談ください。
食事の時間がバラバラですが薬の服用に影響はないですか?
治療の中心となる抗ウイルス薬はウイルスの増殖を防止する薬です。食事の時間が不規則だったとしても、医師から指示があった回数を守って服用しましょう。なお、飲み忘れたからといって、一気に2回分飲むことはお控えください。飲み忘れがあった場合、次回から指示通りに服用し、飲み忘れがあったことを次回診療日に主治医にお伝えください。
患部を手で触っても大丈夫ですか?
手を介して他人に感染することはありませんが、水ぼうそうを発症したことがない方はウイルスに感染して水ぼうそうを発症することがあります。そのため、小さなお子様や妊婦の方にはなるべく接触しないように心がけましょう。