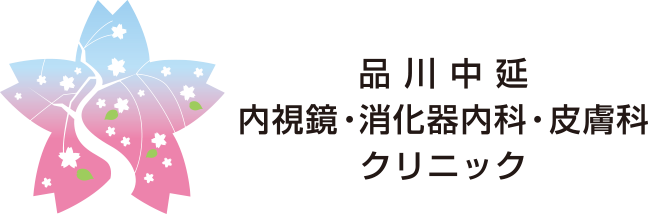過敏性腸症候群(IBS)について

過敏性腸症候群は、内視鏡検査を行っても潰瘍やポリープ、がんなどの器質的異常が発見されないにもかかわらず、腹痛や腹部膨満感に伴って便秘や下痢などの便通異常が長期にわたり続く病気です。
発症原因ははっきりしておらず、大腸の知覚過敏や機能不全などが影響しているのではないかと考えられています。急に発生する激しい腹痛や慢性的な便秘・下痢により日常生活に支障をきたし、生活の質(QOL)の大幅な低下を招きます。当院では、問診や検査により状態を把握し、大腸機能を回復させる適切な薬を使用して治療を行っています。お困りの症状があれば、一度当院までご相談ください。
過敏性腸症候群の症状
過敏性腸症候群は、腹痛や腹部膨満感に伴って便通異常が起こります。症状に応じて便秘型・下痢型・便秘が交互に起こる交代型の3種類に分けられます。腹痛症状は急激に起こることもあれば、鈍い痛みが続くこともあり、排便により症状が落ち着きます。こうした症状は不安や緊張などのストレスや食事がきっかけとなって発生し、睡眠中は症状が起こりません。また、腹鳴やガスの頻発、倦怠感、頭痛、集中力の低下、不安感、抑うつなどの症状を示すこともあります。
下痢型
緊張や不安がきっかけとなり、急激な腹痛とともに激しい下痢が起こります。通学や通勤中に症状が起こり、生活に影響を及ぼす恐れがあります。
便秘型
腸管がけいれんし便が腸内に残ることが原因となります。強い腹痛とともに便秘が繰り返し起こり、いきんでもウサギのようなコロコロした糞便しか出ず、残便感があります。
交代型
腹痛とともに便秘と下痢が交互に繰り返し起こります。
過敏性腸症候群の原因
原因ははっきりとしていませんが、消化管の蠕動運動の異常や知覚過敏、ストレスなどが関与しているといわれています。消化管機能は自律神経によって制御されており、ストレスを受けることで自律神経が失調すると、蠕動運動に異常が起こります。また、感染性腸炎により過敏性腸症候群を発症することも判明しており、免疫異常も関与しているのではないかといわれています。
過敏性腸症候群になりやすい
年齢・体質・性格
体質
生活習慣が乱れている方、遺伝的要因がある方、ストレスにより体調を崩しやすい方は発症リスクが高いです。
性格
真面目な性格や内向的な性格の方は過敏性腸症候群を発症しやすいです。こうした性格の方は、日常の様々な変化にストレスを感じ、自律神経が失調することで過敏性腸症候群の発症を招きます。
ストレスとうまく付き合っていく
現代はストレスを感じる場面が多く、完全にストレスをなくすことは不可能です。匂いや風、温度変化、物音などちょっとしたことでもストレスは感じてしまいます。また、ストレスを断ち切ろうとすることで、よりストレスを溜めることにもなります。ストレスと上手く向き合い、スポーツや趣味などご自身がリフレッシュできる時間を設けましょう。
過敏性腸症候群の診断
過敏性腸症候群で起こる症状は他の病気でも見られるため、まずは大腸カメラ検査によりがんや炎症性変化などの器質的病変の有無を調べます。器質的病変が見つからないにもかかわらず、腹痛に伴って便通異常が慢性化している場合は過敏性腸症候群が疑われます。器質的異常がないことが分かれば、問診で得た情報と世界的診断基準であるRome基準を参考にして診断を下します。
現在では、2016年に制定されたRomeⅣ(R4)が基準として用いられています。
RomeⅣの基準
- 排便によって症状が変わる
- 便の形状(外観)が症状によって変わる
- 排便頻度が症状によって変わる
上記のような症状が6ヶ月以上前から継続的に起きており、直近3ヶ月のうち少なくとも週1回以上症状があり、RomeⅣの基準に2つ以上該当する場合、過敏性腸症候群の診断となります。
器質的異常がないことが前提となるため、血液検査・便検査・尿検査・大腸カメラ検査により有無を調べます。なお、Rome基準でも結果に誤りが出ることもあるので、基準を満たしていなかったとしても医師の判断により過敏性腸症候群の治療を進めることがあります。
過敏性腸症候群の治療
現在のところ発症原因ははっきりしておらず、完治させる治療法が確立されていないため症状を解消するには時間を要します。命を落とすような重篤な病気ではないものの、仕事や学業、日常生活に影響が出るため、早期治療が欠かせません。治療は各患者様の状態・タイプに応じた適切な方法で行います。当院では、薬物療法や食事など生活習慣の改善指導などを実施しています。また、症状に限らず日常生活で悩んでいることをお聞きし、普段通り過ごせるようにアドバイスも実施しています。
生活習慣の改善
睡眠・休息時間をしっかり取り、生活習慣を正すことで症状の改善が期待できます。香辛料などの刺激物やアルコールは消化器症状の悪化を招くため注意しましょう。なお、急激に生活習慣を変えようとするとストレスを感じてしまうため、医師の指示にしたがって無理のない範囲で行いましょう。
運動療法

やや早足での散歩や水泳など軽い有酸素運動を習慣化することで腸の機能の改善が期待できます。また、ストレッチをこまめに行うことも症状の緩和に繋がります。
薬物療法
便秘や下痢など症状に応じた薬を使用します。薬は様々な種類があり、適切な処方となるよう経過を確認して適宜調整します。また、必要に応じて抗うつ薬や抗不安薬、漢方薬、乳酸菌・酪酸菌製剤などを使用することもあります。