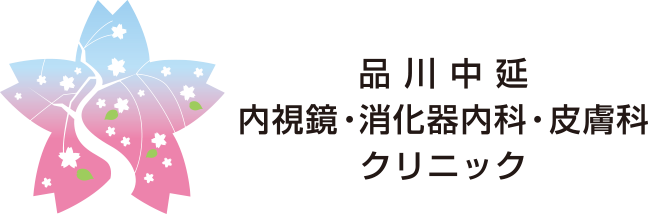機能性ディスペプシア(FD)
について

機能性ディスペプシアとは、検査を受けても異常が見つからないにもかかわらず、胃の違和感や不快感、胃もたれ、みぞおち付近の痛み(心窩部痛)などの症状が起こる病気です。病名にある「ディスペプシア」とは医療用語で「胃の不調」を表す単語です。
当院では、胃腸症状の原因を様々な検査を通じて詳しく調べ、適切な治療に繋げています。お悩みの症状があれば、当院までお気軽にご相談ください。
機能性ディスペプシアの症状
機能性ディスペプシアの症状は、食後の不快感(食後愁訴症候群)とみぞおち付近の痛み(心窩部痛症候群)の2つにグループ分けられます。
食後愁訴症候群
食後に胃の不快感や胃もたれ、早期膨満感、吐き気や嘔吐などが起こるタイプです。
心窩部痛症候群
みぞおち付近の痛み(心窩部痛)やみぞおちが焼ける感覚(心窩部灼熱感)が起こるタイプです。心窩部痛は心臓の圧迫感として感じられることもあります。
機能性ディスペプシアの原因
機能性ディスペプシアは、精神的なストレスや胃の知覚過敏、蠕動運動の異常など様々な要因が重なることで発症すると考えられています。
蠕動運動の異常
体内に入った食物は消化管壁が拡張・収縮を繰り返しながら次の消化管に送られていきます。この消化管の動きを蠕動運動といいます。蠕動運動に異常が起こると食物が次の消化管に送られず、胃もたれや胃痛、嘔吐などの症状が起こります。
神経系の異常(知覚過敏)
胃は食物を一時的に溜め込む機能があり、満腹になるまで食べると胃が膨れます。通常であればこの状態で胃痛が生じることは滅多にないですが、胃の知覚機能に異常が起きていると、少量の食物が胃に入ってきただけでも、みぞおち付近に痛み(心窩部痛)が起こることがあります。
精神的ストレス
脳と消化管は自律神経を介して相互に影響し合う関係にあり、これを「脳腸相関」といいます。精神的なストレスを受けて自律神経が乱れた場合、消化管機能に異常が起こり、機能性ディスペプシアに繋がります。
機能性ディスペプシアの
診断・検査
機能性ディスペプシアと同じ症状を示す病気は多数あり、例えば、胃・十二指腸潰瘍、食道がん、胃がん、大腸がんなどが挙げられます。そのため、機能性ディスペプシアの確定診断には、これら病気の除外診断が必要です。検査を行っても器質的異常が見つからないにもかかわらず、食後愁訴症候群や心窩部痛症候群が生じている場合は機能性ディスペプシアが疑われます。
以下が機能性ディスペプシアの診断を下すために行う検査です。
胃カメラ検査

胃カメラ検査は、内視鏡スコープを口や鼻から挿入し、食道・胃・十二指腸などの上部消化管粘膜を直接観察します。潰瘍やがんが見つかった場合は、その病気に有効な治療を行います。胃カメラ検査は苦痛を感じるイメージが強いですが、当院では鎮静剤の使用など様々な工夫により苦痛を最小限に抑えています。安心してご相談ください。
超音波検査(超音波エコー検査)
 超音波検査は、胃カメラ検査では確認が難しい肝臓や胆のう、膵臓、脾臓、腎臓などの腹部臓器を調べる画像診断です。異常が見つかった場合は適切な治療を行います。検査は超音波を照射するのみで身体に負担がかかることはありません。しかし、正確な検査を行うために当日は食事を抜いたうえでお越しいただきます。
超音波検査は、胃カメラ検査では確認が難しい肝臓や胆のう、膵臓、脾臓、腎臓などの腹部臓器を調べる画像診断です。異常が見つかった場合は適切な治療を行います。検査は超音波を照射するのみで身体に負担がかかることはありません。しかし、正確な検査を行うために当日は食事を抜いたうえでお越しいただきます。
機能性ディスペプシアの治療
機能性ディスペプシアは前述の通り様々な原因が考えられます。まずは食事や運動など生活習慣の改善を試みます。それでも症状が改善しない場合は薬物療法を行います。
食事療法
機能性ディスペプシアの原因の1つに胃酸の分泌過多も挙げられるため、消化しやすい食事メニューとなるようにアドバイスを行います。動物性脂肪が豊富な肉類や糖質が豊富な食品、香辛料などの刺激物、アルコール類の過剰摂取は控えましょう。喫煙も消化機能の悪化を招くため、禁煙に取り組みましょう。
薬物療法
薬物療法では原因に応じて、胃酸の分泌を抑える胃酸分泌抑制薬(プロトンポンプ阻害薬やH2ブロッカーなど)、胃腸の運動を促す消化管運動機能促進薬などを使用します。また、精神的なストレスが原因となっていることもあるため、その場合は漢方薬や抗うつ剤を使用することがあります。