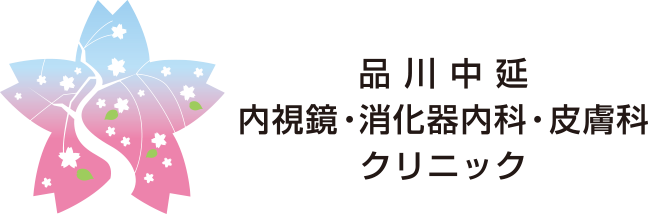皮膚科について
 皮膚科は、皮膚・爪・毛に起こった症状・病気を専門とする診療科です。なお、皮膚症状を引き起こす病気は様々で、同じ症状だったとしても原因疾患は異なるケースがあります。また、内科疾患が原因となって皮膚症状が起きていることもあります。数日で症状が解消することもありますが、原因疾患によっては長期の治療とともにスキンケアが必要になることもあります。
皮膚科は、皮膚・爪・毛に起こった症状・病気を専門とする診療科です。なお、皮膚症状を引き起こす病気は様々で、同じ症状だったとしても原因疾患は異なるケースがあります。また、内科疾患が原因となって皮膚症状が起きていることもあります。数日で症状が解消することもありますが、原因疾患によっては長期の治療とともにスキンケアが必要になることもあります。
当院では問診や検査から皮膚症状の原因を特定し、内科疾患が原因となっている場合は内科と連携して治療に取り組んでいます。お悩みの症状があれば、お気軽に当院までご相談ください。
皮膚科受診で多い症状と病気
かゆみ
かゆみは炎症など様々な原因が考えられます。適切な治療を行うためには、まずは原因を特定することが必要です。かゆみは身体を守るための防御反応の1つですが、気になって掻いてしまうと悪化する可能性があるため、気になる方は早めに当院までご相談ください。
かぶれ(接触皮膚炎)
かぶれとは何らかの物質が皮膚に触れることで発生する炎症で、医療用語では「接触皮膚炎」と呼ばれます。接触皮膚炎は、外部からの強い刺激により起こる「刺激性接触皮膚炎」と、アレルギー反応として生じる「アレルギー性接触皮膚炎」に大別されます。予防のためにはいずれの場合も原因物質や刺激への接触を避けることが必要です。アレルギー性接触皮膚炎では、アレルゲンを調べるためにパッチテストを実施することがあります。
湿疹
湿疹は、皮膚に発生する炎症の総称で、赤みやブツブツ、小さな水疱などが現れ、かゆみや痛みを伴うこともあります。湿疹は内的要因と外的要因が複雑に絡み合って起こるといわれており、原因がはっきりしないこともあります。内的要因には乾燥による皮膚のバリア機能の低下、アトピー素因、健康状態などが挙げられます。一方、外的要因には真菌や細菌などの病原体、アレルゲン、薬剤、化学物質、金属、日光などが挙げられます。
蕁麻疹
蕁麻疹とは、突然皮膚に強いかゆみを伴う腫れが発生する皮膚疾患です。ほとんどの場合は数分から24時間以内に消失しますが、1ヶ月以上にわたって症状を繰り返す慢性蕁麻疹が起こることもあります。原因は多岐にわたり、ウイルス・細菌感染、ストレス、疲労、飲食物、薬剤などが挙げられます。なお、血液検査などの検査を行っても原因がはっきりしないこともあります。治療は抗ヒスタミン薬を用いた薬物療法を行います。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う湿疹が慢性的に寛解と再燃を繰り返すアレルギー疾患です。皮膚が乾燥するとバリア機能が低下するため、抗原などが皮膚内に侵入して炎症が引き起こされます。アトピー素因がある方は皮膚にアレルギー反応が起こりやすいため、アレルゲンをなるべく避けるようにしましょう。また、強いかゆみを示しますが、掻いてしまうと悪化する可能性があります。かゆみを軽減するため炎症を抑える治療を早めに受けましょう。また、患者様自身でも日頃からスキンケアを行って肌の乾燥を防ぐことも必要です。そのため、当院では適切なスキンケアの指導も行っています。
ニキビ
ニキビは、皮脂が過剰に分泌され毛穴が詰まることで起こります。毛穴が皮脂によって詰まった状態ではアクネ菌が繁殖し、悪化していきます。特に顔や背中など皮脂が分泌されやすい部分に起こりやすいです。また、子どもの頃にできるニキビに比べ、成人になってからできるニキビは治りが悪い傾向があります。なお、治療が遅れると色素沈着や凹みなどのニキビ跡として残ってしまう可能性があるため、早めに治療を開始することが大切です。治療はニキビの状態に応じた適切な外用薬や内服薬などを用いて行います。ニキビ跡にならないように、早めに当院までご相談ください。
たこ・ウオノメ
たこ・ウオノメは皮膚が部分的に繰り返し刺激を受けることで発生する角質肥厚です。たこは皮膚表面の角質肥厚で、足裏以外にも指など身体の様々な部分に発生することがあります。なお、痛みを感じることはほとんどありません。一方、ウオノメは足裏にできることが多く、中心に硬い芯ができます。歩行時にこの芯が神経を圧迫することで強い痛みを感じます。
注意が必要なものとして足底疣贅があります。これはウオノメと同じく足裏に発生しますが、ウイルス感染が原因となり、不適切なケアを行うと病変が広がる恐れがあります。そのため、足裏に気になる病変が発生している場合、一度当院までご相談ください。
いぼ
いぼには様々な種類があり、ヒトパピローマウイルス(HPV)への感染が原因となる尋常性疣贅、伝染性軟属腫ウイルスが原因の水いぼ、紫外線や加齢が原因となる脂漏性角化症などが挙げられます。自然治癒することもありますが、種類によっては他の場所に広がってしまったり、周囲の方に感染してしまったりすることがあります。気になって掻いてしまうと感染する可能性があるため注意が必要です。このような理由から、いぼができた場合は早めに当院までご相談ください。
治療は内服薬や外用薬を用いた薬物療法、液体窒素を使った冷凍凝固法、摘出術などがあり、いぼの種類や数に応じて適切な治療を行います。
水虫(白癬)
水虫(白癬)は、真菌の仲間である白癬菌が角層に感染することで発症する病気です。白癬菌は足に感染することが多いですが、全身の皮膚に感染する可能性があり、感染部位に応じて頭部白癬、手白癬、爪白癬、体部白癬、股部白癬と呼ばれます。状態に応じて内服薬や外用薬を用いた治療を行います。
ヘルペス
ヘルペスは単純ヘルペスウイルスの感染が原因となる感染症で、発疹や潰瘍などの病変が発生します。ヘルペスは口唇ヘルペスや顔面ヘルペスを引き起こす1型と、臀部ヘルペスや性器ヘルペスを引き起こす2型に分類されます。1型ヘルペスウイルスは初感染では症状が現れないこともあります。2型ヘルペスウイルスでは、女性が初感染した場合、激痛や高熱などの症状が起こることもあります。抗ウイルス薬(外用薬・内服薬)を用いた薬物療法が有効です。放置していると病状が悪化する恐れがあるため、発疹が出る前に違和感などがあれば、すぐに当院まで受診ください。
帯状疱疹
帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスの感染が原因となります。幼少期の初感染時は水ぼうそうが起こります。症状が改善した後もウイルスは神経節に潜伏し続け、ストレスや疲労、睡眠不足、加齢などによって免疫力が低下したことをきっかけに再活性化し、帯状疱疹が起こります。身体の左右いずれかの神経に沿う形で、赤い斑点や小さな水ぶくれが帯状に発生し、ピリピリとした神経痛を伴います。全身に症状が起こる可能性があり、耳周辺に発生した場合は耳鳴りやめまい、目の周囲に発生した場合は結膜炎や角膜炎、顔面に発生した場合は顔面神経麻痺などの症状を示すことがあります。
帯状疱疹の皮疹が治まった後も、長期間神経痛が続くことがあり、これを「帯状疱疹後神経痛」といいます。
フケ症(脂漏性皮膚炎)
フケ症とは、白い粉のような角質が剥がれ落ちる状態です。こうした症状は、脂漏性皮膚炎やアトピー性皮膚炎、接触皮膚炎などで起こります。原因の1つとなる脂漏性皮膚炎は皮脂の分泌が多い顔面や頭部、耳介などに発生する炎症疾患で、赤みやかゆみを伴います。乳児に発生する乳児型では生後1年ほどで自然治癒することがほとんどですが、思春期以降に発生する成人型の場合は慢性的に繰り返し起こることが多いです。真菌の仲間であるマラセチア(皮膚の常在菌)が発症に関わっていると考えられており、抗真菌外用薬やステロイド外用薬を用いた薬物療法を行います。また、日頃のスキンケアも大切で、過剰に皮脂が蓄積しないように洗顔やシャンプーなどを行いましょう。
乾癬
乾癬とは、皮膚表面が赤く盛り上がり、その上に鱗屑(白いかさぶた)ができる慢性の炎症疾患です。赤い発疹は境界がはっきりしていることが特徴です。機械的刺激を受けやすい部位に発生することが多く、形状やサイズは様々です。悪化に伴って全身に広がる恐れがあります。遺伝的要因に環境因子が加わることで発症に至るといわれています。なお、感染リスクはありません。治療はステロイド外用薬やビタミンD3外用薬を用いた薬物療法が中心となりますが、紫外線療法を併用することもあります。
アレルギー性鼻炎
アレルギー性鼻炎は、花粉やダニなどのアレルゲンに対する免疫の過剰反応で、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・目のかゆみなどの症状を引き起こします。花粉が原因の「季節性」と、ダニやハウスダストなどが原因の「通年性」に分けられます。症状がある場合は、アレルゲンの特定と回避が大切で、生活に合った治療で症状のコントロールが可能です。当院では、治療として舌下免疫療法に対応しております。
舌下免疫療法とは
舌下免疫療法は、スギ花粉やダニが原因のアレルギー性鼻炎に対して、アレルゲンを少量ずつ舌の下に投与し、体を慣らして体質改善を目指す治療法です。自宅で服用でき、痛みもなく、根本治療が期待できます。治療には数年の継続が必要です。