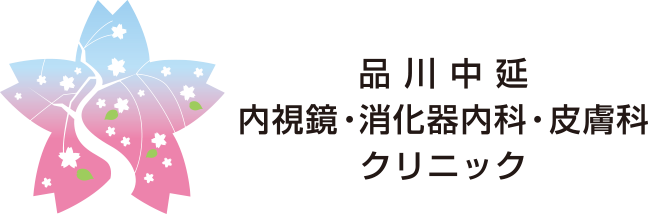- 大腸ポリープは大腸がんになる?
- 大腸ポリープの症状
- 大腸ポリープの切除
- 大腸ポリープ切除方法
- 大腸ポリープを切除後の食事制限は?
- 大腸ポリープ切除後の食事以外に注意すること
- 大腸ポリープ切除は保険でいくらもらえる?
大腸ポリープは大腸がんになる?

大腸ポリープは腫瘍性と非腫瘍性に大別されます。腫瘍性ポリープは、さらに良性の腺腫とがんに分けられますが、腺腫であることがほとんどです。なお、腺腫は時間の経過に伴ってがん化する恐れがあるため注意が必要です。
大腸ポリープは直腸やS状結腸付近、盲腸付近に発生しやすいです。
大腸ポリープの症状
大腸ポリープの症状は発生場所に応じて違いがあります。ポリープが小さい場合は自覚症状が乏しいですが、大きくなっていくとポリープに便が接触することで出血し、血便が出ることが多くなります。特に肛門付近を通過する便は腸で水分を吸収された硬い便となるため、肛門付近にできたポリープは小さく盛り上がりが少ない場合でも血便が出やすくなります。一方、小腸付近を通過する便は水分が多い柔らかい便となるため、ポリープが大きく盛り上がったものでも血便が出にくいです。
大腸ポリープは放置していると、がんに進行する可能性があるため、発症箇所がどこであったとしても早期治療が大切です。気になる症状があれば早めに当院までご相談ください。
大腸ポリープの切除

大腸カメラ検査にてポリープが発見された場合、検査中にポリープを切除する日帰り手術を行います。そのため、切除のために後日お越しいただく必要はありません。なお、切除後1週間ほどは、出血リスクを抑えるためにも運動や入浴などの血流を促すような行動は控えていただきます。また、出血が生じた場合に遠方にいるとすぐに止血処置を行えないため、出張や旅行もお控えください。食事は1週間ほど一部制限があります。
ポリープのサイズや数次第では切除に入院を伴うため、この場合は連携している高度医療機関をご紹介します。
大腸ポリープ切除方法
ポリープは、内視鏡先端から出したスネアと呼ばれる金属製の輪を病変に引っ掛けて締め付け切除しますが、以下のように3つの方法に分けられます。切除したポリープを病理検査に回すことで確定診断を下せます。
ポリペクトミー
ポリープ切除のうち、最も古典的な術式です。ポリープをスネアで高周波電流を流すことで焼き切ります。電流により止血されますが、熱が深層にまで伝わった場合、切除後数日は出血や穿孔が発生するリスクがあります。必要に応じてクリップで出血、穿孔の予防処置を行います。
コールドポリペクトミー
コールドポリペクトミーは高周波電流を使わず、締め付ける力のみで切除する術式で、当院ではこの術式を利用することが多いです。術後出血のリスクが低いのがこの治療法の長所です。
内視鏡的粘膜切除術(EMR)
平坦なポリープにはスネアを引っかけにくいです。内視鏡的粘膜切除術は、ポリープ下層に生理食塩水を流し込み、ポリープが盛り上がった状態で周りの粘膜ごとスネアを引っかけて、高周波電流により焼き切ります。
大腸ポリープを切除後の食事制限は?
検査当日の食事は消化に良いメニューにしましょう。例えば、素うどんや豆腐、白粥、ヨーグルト、ゼリー、プリンなどがお勧めです。検査の翌日から少しずついつも通りの食事に戻していただきますが、1週間ほどは刺激物の摂取はお控えください。
検査後に腹痛や出血が起きた場合、すぐに当院までご相談ください。
大腸ポリープ切除後の食事以外に注意すること
運動
激しい運動は血圧や腹圧が上がるため出血のリスクが高まります。ポリープの大きさや術式によって違いがありますが、切除後1週間ほどは激しい運動は控えましょう。
出張、旅行
ポリープ切除後は出血のリスクがあるため、出張や旅行など遠方への移動は控えてください。出血が起きた場合、対応が遅れる恐れがあるため、この点を踏まえた上でスケジュールの調整をお願いします。ポリープの大きさや術式によって違いがありますが、切除後7日ほどは遠方への移動は控えましょう。
入浴
長時間の入浴やサウナは血圧が高くなり血流を促すため、ポリープ切除後は出血リスクが高まります。術後しばらくの間はシャワー浴でお済ませください。
薬
血液をサラサラにする抗血栓薬を飲まれている場合、大腸カメラによって出血する恐れがあるため、検査前に一時休薬していただきます。服用の再開は医師の指示にしたがってください。
飲酒
血流をよくして出血を助長します。1週間は禁酒が必要です。
出血
大腸ポリープの切除後1週間ほどは便に血液が混ざっていないかチェックが必要です。血液が少量混じっている程度であれば大丈夫ですが、大量に出血している場合はすぐに大腸カメラ検査による止血処置が必要です。不安なことがあれば、お気軽に当院までご相談ください。
大腸ポリープ切除は保険でいくらもらえる?
保険会社や契約内容によりますが、生命保険や入院保険に加入していると、申請することで手術給付金を受給できる可能性があります。申請にあたって保険会社から医師の診断書を求められます。当院でも対応していますが、診療費とは別に診断書の作成費を頂いています。また、書類ができるまでに少しお時間がかかるので、ご理解のほどお願いします。
申請対象となるか分からない場合、加入中の保険会社にご連絡ください。