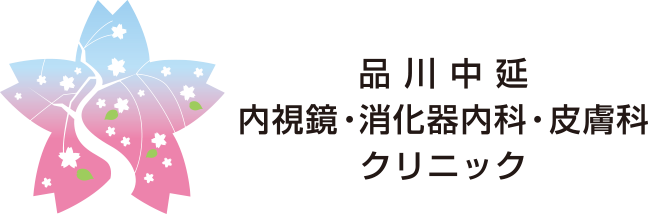肛門内科について

肛門内科では、肛門周囲に発生する出血や腫れなどの症状・病気を対象とした診療科です。肛門内科で相談される病気として多いのは、いぼ痔(内痔核・外痔核)、切れ痔、痔ろうなどです。
当院では、患者様の負担を最小限に抑えられるように努めており、プライバシー保護の観点から受付にてお悩みの症状などをお伺いすることはありません。お悩みの症状があれば、お気軽に当院までご相談ください。
よくある肛門の症状について
いぼのような出っ張り
肛門や肛門付近に出っ張りを感じる場合、いぼ痔や肛門ポリープ、粘膜脱症候群、大腸ポリープ、大腸がんなどの可能性があります。特に大腸ポリープはがん化するリスクがあるため注意が必要です。大腸カメラ検査中に大腸ポリープが発見された場合、将来の大腸がんの発症を防ぐために検査中にポリープを切除します。
出血を生じる
肛門周囲から出血が起きている場合は痔の可能性があります。トイレットペーパーに少量の血液が付着している程度であれば切れ痔が疑われ、大量出血となっている場合はいぼ痔が疑われます。その他、大腸ポリープ、大腸がん、潰瘍性大腸炎、クローン病などの可能性もあります。また、出血のほか、粘液便や黒色便が排泄されることもあります。
痛みを生じる
痛みといっても感じ方は様々で、排便時に痛みを感じるケースや重量物を持ち上げる際に感じるケース、安静時にズキズキとした痛みを感じるケースなどがあります。肛門に痛みを感じる場合、切れ痔や嵌頓痔核、血栓性外痔核、肛門周囲膿瘍などが疑われます。痛みを感じるきっかけを詳しく教えていただけるとスムーズな診断に繋がります。
かゆみを生じる
肛門にかゆみを感じる場合、カビやカンジダ菌、白癬菌などの真菌の感染が疑われます。また、肛門周囲皮膚炎により清潔な状態を維持するために過剰にケアを行ってしまった場合も、炎症が発生してかゆみを感じることがあります。治療は抗真菌薬を使用します。
肛門内科でよくある病気
いぼ痔
いぼ痔とは、肛門に負荷がかかることで肛門周囲の血管がうっ血してできたいぼ状の腫れです。肛門内側の直腸粘膜にできたものは「内痔核」と呼ばれ、肛門外側の皮膚にできたものは「外痔核」と呼ばれます。それぞれ症状や治療法に違いがあります。
内痔核
内痔核は肛門内側の直腸粘膜に発生したいぼ痔です。直腸粘膜には知覚神経がないため痛みが起こることはなく、放置されることも少なくありません。なお、排便時に便が痔核に擦れて大量出血することがあり、これが受診のきっかけとなることが多いです。また、痔核が肛門外に飛び出して、下着と擦れることなどにより痛みが起こるようになります。初期は痔核が肛門外に脱出しても自然に元の位置に戻りますが、悪化に伴って指で押し込まないと戻らなくなり、最終的には指で押しても脱出したままの状態となります。脱出した痔核が肛門周囲の筋肉に圧迫されることで血栓が作られ、激しい痛みが起こることがあります。
外痔核
肛門外側の皮膚に発生したいぼ痔です。皮膚には知覚神経が通っているため、痛みを感じます。また、外痔核の血流が悪化して血栓ができた場合、ズキズキとした激しい痛みが起こるようになります。治療は薬物療法を実施します。
切れ痔
切れ痔とは、下痢による勢いの強い便や便秘による硬く太い便の通過などによって、肛門の皮膚が損傷して切れた状態です。出血はトイレットペーパーに少し血が付着する程度ですが、激しい痛みが起こります。初期は軟膏や座薬、便を柔らかくする薬によって改善が見込めますが、便秘がちな方は切れ痔の再発・悪化リスクが高いため便秘の治療も並行して行います。損傷部が瘢痕化して肛門が狭窄した場合、手術を行います。なお、手術が必要になる場合は連携先の医療機関をご紹介します。
痔瘻(じろう)
痔ろうは、肛門周囲の皮膚に繋がるトンネル(瘻管)が形成された状態です。肛門と直腸の境目には歯状線があり、歯状線には肛門陰窩と呼ばれる小さな穴が並んでいます。この肛門陰窩に便が侵入して細菌に感染し、化膿することで肛門周囲膿瘍が起こります。膿は肛門周囲の皮膚組織を掘っていき、最後は皮膚にまで繋がるトンネルが形成されて膿が体外に排出されます。このトンネルが残った状態を痔ろうといいます。肛門周囲膿瘍では細菌感染により炎症が発生しているため痛みや発熱などが起こりますが、痔ろうに至ると膿が排出されるのでこれらの症状は落ち着きます。なお、痔ろうを放置すると瘻管が複雑化していき、肛門機能が障害される恐れがあります。また、大腸がんに繋がる可能性もあります。そのため、早い段階で治療を行うことが重要です。痔ろうの治療は手術となりますが、肛門機能に障害を起こさないように細心の注意が必要となるため、連携先の医療機関をご紹介します。